※ この記事にはアフィリエイトリンクが含まれます
お客さん向けの資料を作った際に、
- 技術的には正しいのに、「難しくてわからない」と言われる
- 図や文章を増やしたのに、なぜか伝わらない
- 打ち合わせで「つまりどういうことですか?」と聞かれてしまう
こんな経験、ありませんか?
実は、”技術的に正確な資料”と”お客さんに伝わる資料”は、似ているようで全く別物なんです。
エンジニアが当たり前だと思っている言葉や図も、お客さんから見ると「専門用語ばっかり」に見えてしまうことがあります。
お客さんに伝わる資料を作るには、「相手が理解できるようにデザインする」ことが大切です。
この記事では、「ITエンジニアがお客さんにわかりやすい資料を作るための7つのコツ」を、具体例を交えながら紹介します。
この記事を読み終える頃には、
- 提案資料や打ち合わせ資料を”理解される形”に整える方法
- 伝わりやすいスライド構成や表現のコツ
がわかるようになります。
それでは、早速みていきましょう。
「伝わる資料」とは?
「わかりやすい資料を作りたい」と思っても、そもそも”伝わる資料”ってどんなもの?と感じる人も多いと思います。
ここで一度、目的を整理しておきましょう。
“伝わる資料”とは、お客さんが内容をすぐに理解できて、次のアクションに移れる資料のことです。例えば提案資料なら「この案でいこう」と判断してもらえること、報告書なら「状況がすぐにわかる」ことがゴールになります。
逆に、専門的すぎたり構成が複雑だったりすると、お客さんは「結局何が言いたいの?」と混乱してしまいます。
どれだけ技術的に正かったとしても、伝わらなければ意味がないんです。
つまり、”伝える資料”ではなく、“相手が理解できる資料”を目指すことが大切です。
資料を作るときは、まず次の3つを意識してみましょう。
- お客さんが理解できる言葉で書くこと
- お客さんが知りたい順番で構成すること
- お客さんが迷わない見せ方をすること
この3つを意識するだけでも、資料の伝わり方はガラッと変わります。
次は、具体的にどう工夫すればお客さんに「わかりやすい」と感じてもらえるか、7つのコツを紹介します。
コツ① 専門用語は「かみ砕き+具体例」で説明する
エンジニアが作る資料で一番多い「伝わらない原因」は、ずばり専門用語の使いすぎです。
私たちにとっては日常的な言葉でも、お客さんからすると「聞いたことあるけどよくわからない」というケースがほとんどです。
例えば、
「APIで外部サービスと連携しています」
と書いても、IT業界以外の人にはピンときません。
これを、次のように少しだけ言い換えてみましょう。
「アプリ同士をつなぐ”受付口”のような仕組み(API)を使って、他のサービスとやり取りしています」
たったこれだけで、お客さんの理解度は大きく変わるでしょう。
かみ砕き方のコツ
専門用語を避ける必要はありません。
むしろ、「きちんとした用語を使いながら、誰でもイメージできるように説明する」ことが大事です。
ポイントは3つあります。
- 比喩を使う
例:「サーバー」→「データを保管して配る倉庫のようなもの」 - 具体例を出す
例:「ログを取る」→「アクセス記録を残すこと」 - 図で補う
文章で説明しにくい場合は、シンプルなイラストを添えるだけでも理解が早くなります。
適切な説明ができるようになるためには、まず自分が専門用語を正しく理解していることが必要になります。自信がない方は、こちらの本がわかりやすく参考になりますので、辞典代わりに持っておくと良いでしょう。
コツ② 1スライド1メッセージを意識する
資料を作っていると、「せっかくだからこのページに全部まとめちゃおう」と思って、情報を詰め込みすぎてしまうことはありませんか?
でも、お客さんからすると、情報が多い=理解しやすいではなく、どこを見ればいいのかわからないになってしまいます。
伝わる資料は”1ページ=1メッセージ”
わかりやすい資料は、1ページごとに「伝えたいことが一つ」に絞られています。
例えば、
- 「システム全体の流れを説明するページ」
- 「導入メリットをまとめたページ」
- 「スケジュールを示すページ」
というように、1スライドで1つの話題に集中することで、お客さんは迷わず理解できます。
タイトルで”何を伝えたいのか”を明確にする
もう一つのポイントは、スライドタイトルの書き方です。
単に「概要」「課題」「提案内容」と書くよりも、伝えたい内容を文章にする方が効果的です。
タイトルを見ただけで要点が伝わると、お客さんは内容をスムーズに理解できます。
情報を整理する小ワザ
- 箇条書きは3〜5行以内にまとめる
- 図や表を使う場合は「何を伝える図か」を一言添える
- 詳細は補足ページにまわして、メインはシンプルに
「1スライド=1メッセージ」を意識するだけで、お客さんが”理解しやすい”と感じる資料に変わります。
コツ③ 構成は「概要→詳細→補足」で進める
資料を作るときに意外と難しいのが「どんな順番で説明するか」です。
技術的な説明を先に入れたくなる気持ちはありますが、お客さんにとっては「なぜその話をしているのか」がわからず、途中でついていけなくなることがあります。
大事なのは”お客さんの理解の順番”に合わせること
多くの資料は、「作り手が説明したい順」で並べられています。
その基本が、「概要→詳細→補足」という流れです。
例えば、提案資料の場合、
- 概要(全体像・目的)
まず「何を解決したいのか」「どんな方向性なのか」をざっくり示します。 - 詳細(仕組み・手段)
次に「どうやって実現するのか」を説明します。図やステップを使うと理解しやすいです。 - 補足(条件・リスク・コストなど)
最後に「前提条件」や「想定課題」をまとめておくと、信頼度が上がります。
なぜこの順番が大事なのか
お客さんは、最初に全体像がつかめないと、途中の説明が頭に入ってきません。
「何の話か」がわかったうえで詳細を見ることで、理解がぐっと早くなります。
たとえば——
- いきなりシステム構成図を見せるより、「このシステムは〇〇の作業を自動化するためのものです」と前置きしてから説明する
- 手順やフローを見せるときも、「全体の流れはこのようになります」と先に概要を示す
このように、お客さんが“話の地図”を持てるように構成することが、伝わる資料づくりの基本です。
コツ④ 図・表・フローを積極的に使う
どれだけ説明が丁寧でも、文字ばかりの資料はお客さんにとって負担が大きいものです。
逆に、図や表を使って視覚的に伝えるだけで、理解度は一気に上がります。
図・表・フローの使い分け
資料を作るときは、次のように目的ごとに使い分けるのがコツです。
| 種類 | 向いている内容 | 例 |
|---|---|---|
| 図(構成図・イラスト) | 関係性・全体像を見せたいとき | システム構成、画面遷移図など |
| 表(比較・整理) | 違いや項目を整理したいとき | 現行と改善後の比較、料金プラン一覧 |
| フロー(流れ) | 手順や時系列を伝えたいとき | 処理の流れ、業務手順 |
例えば、提案書で「現行システムの問題点」を説明するなら、
文章で並べるよりも「現行 → 問題点 → 改善案」をフロー図で見せたほうが、一目で理解できます。
図だけで”概要がつかめる”資料を目指す
良い資料は、ページをパッと見ただけで「何が言いたいのか」がわかります。
そのためには、図や表の中にも「タイトル」や「一言コメント」を入れてあげましょう。
- 「システム構成図」
- 「システム構成図:各部署からのデータを自動集約する仕組み」
ちょっとした補足を入れるだけで、図がぐっと“伝わるもの”に変わります。
コツ⑤ 文字は「少なく・大きく・整理して」配置
資料を作っていると、「説明を丁寧にしよう」と思ってつい文字が多くなってしまうこと、ありませんか?
でも、お客さんが求めているのは”全部を読む資料”ではなく、“見て理解できる資料”です。
そのためには、文字の量と見せ方を工夫することが大切です。
1. 文字はできるだけシンプルに
1枚のスライドに詰め込みすぎると、どれが大事な情報なのか伝わりません。
目安としては、1スライドにつき3〜5行の箇条書きがちょうどいいくらい。
文ではなく、短いフレーズでOKです。
例
- 「システム導入により、業務効率の改善とコスト削減が見込まれます。」
- 「業務効率アップ・コスト削減を実現」
このくらいのほうが、パッと見で頭に入ります。
2. フォントサイズは”遠くからでも読める大きさ”で
打ち合わせやプレゼンでは、資料がモニターやプロジェクターに映し出されることも多いですよね。
そのときに文字が小さいと、それだけで印象が悪くなります。
最低でも20pt以上、理想は24pt以上を目安にしましょう。
見た目がスッキリするだけでなく、読む側のストレスもぐっと減ります。
3. 協調は色よりも”太字”や”余白”で見せる
つい文字を赤くしたくなりますが、色を多用すると逆に見づらくなります。
重要な部分は太字・下線・枠などで強調し、他とのコントラストで目立たせるのがおすすめです。
また、余白を恐れないことも大切です。
余白があると視線が整理され、伝えたいポイントが自然と際立ちます。
コツ⑥ 読み手のレベル・目的に合わせて内容を調整
「同じ資料を見せたのに、反応が全く違う」
そんな経験をしたことはありませんか?
それは、相手の立場や目的が違うからです。
お客さんによって、知りたいこと・関心のあるポイント・理解できるレベルは全く違います。
だからこそ、資料を作るときは”誰に見せるか”を最初に決めておくことが大切です。
相手によって伝え方を変える
同じ内容でも、説明の角度を少し変えるだけで伝わり方が変わります。
代表的なパターンを見てみましょう。
| 相手のタイプ | 興味・関心 | 資料で重視すべきポイント |
|---|---|---|
| 経営層・管理職 | コスト・リスク・効果 | 「どんなメリットがあるのか」「費用対効果」 |
| 現場担当者 | 使いやすさ・運用負担 | 「具体的にどう使うのか」「導入後の流れ」 |
| エンジニア・技術者 | 技術的な詳細・仕組み | 「どう実現しているのか」「技術選定の理由」 |
たとえば同じシステム提案でも、
- 経営層には「コスト削減と業務効率化の成果」を中心に
- 担当者には「操作の流れや運用イメージ」を中心に
と見せ方を変えることで、伝わり方がまるで違ってきます。
コツ⑦ レビューを”非エンジニア”に頼む
「お客さんに伝わるかどうか」をチェックするなら、非エンジニアの視点が欠かせません。
技術的に正しくても、伝わらなければ意味がない
エンジニア同士だと、「この構成ならAWSの方がいいね」みたいな技術トークに流れがちです。
しかしお客さんが求めているのは、
「それでどんなメリットがあるのか」「導入後どう変わるのか」といった効果や安心感。
技術的には完璧でも、言葉が専門的すぎるとお客さんの理解が追いつかず、
「難しそう」「自分たちに合ってるかわからない」と感じてしまうことがあります。
社内の”非エンジニア”に見てもらうだけで気づきが増える
例えば、営業担当や総務の同僚など、
ITに詳しくない人に資料を見てもらうだけで、思いもよらない指摘を受けることがあります。
「このページ、何を伝えたいのかわからなかった」
「“API連携”って、具体的に何ができるの?」
そういったフィードバックは、お客さんが引っかかるポイントそのものです。
ここを改善できれば、資料のわかりやすさは格段に上がります。
伝わる資料=お客さんが次の行動を取りやすい資料
レビューの目的は「完璧な資料を作ること」ではなく、
お客さんが理解し、次のステップに進みやすくすることです。
非エンジニアにレビューをお願いすると、
「この説明でお客さんが前向きに動けるか?」という観点が自然と入ります。
結果として、伝わる資料=行動につながる資料になります。
まとめ
お客さんにわかりやすい資料を作るコツは、
難しい言葉やデザインテクニックではなく、「相手の立場に立つこと」に尽きます。
エンジニアとしてはつい、「技術的に正しいか」「構成が美しいか」に意識が向きがちですが、
お客さんから見れば、“自分たちの課題がどう解決されるか”がすべてです。
その視点を忘れずに、
- 技術説明よりも目的を先に伝える
- 専門用語をかみ砕く
- 図や例え話でイメージを補う
- 非エンジニアにレビューしてもらう
といったポイントを押さえれば、ぐっと伝わる資料になります。

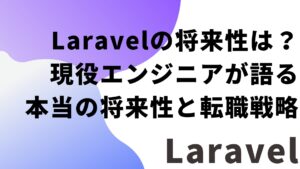

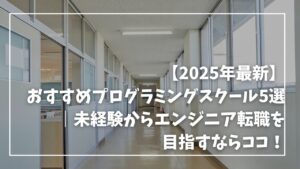
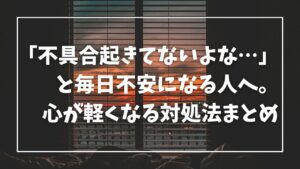
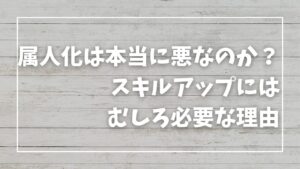
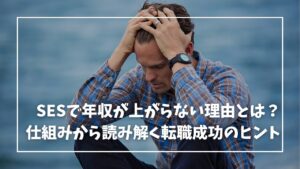
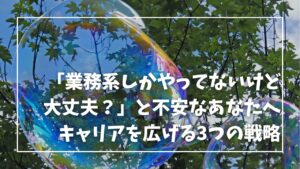
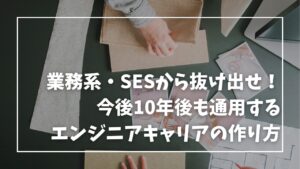
コメント