※ この記事にはアフィリエイトリンクが含まれます
企業の基幹システムや大規模な業務アプリケーションで広く利用されているのがOracle Databaseです。
その基盤となる「データベースの作成」は、Oracleを学ぶうえで避けて通れない大切なステップです。
本記事では、SQL Plusを利用した コマンドベースでのデータベース作成方法 を中心に解説していきます。
データベースを自分の手で立ち上げられるようになれば、Oracleの理解は大きく前進します。
記事の最後には、さらにスキルを伸ばすための おすすめ書籍 や、Oracleスキルを活かしたキャリア形成に役立つ 転職サイト情報 も紹介していますので、ぜひ学びのステップアップに役立ててください。
Oracle Databaseの基本を理解する
まずは、データベース作成に入る前にOracle Databaseそのものの基本を押さえておきましょう。
Oracle Databaseとは
Oracle Databaseは、世界中の企業で利用されている商用RDBMSです。
銀行や通信、製造業など、止まることが許されない大規模システムの基盤として選ばれることが多く、信頼性・拡張性・セキュリティに優れています。
無料で使えるMySQLやPostgreSQLと比べると、ライセンス費用は高額ですが、その分 大規模データ処理や高可用性 を重視した機能が豊富に揃っているのが特徴です。
無償版「Oracle Database XE」
学習や検証を目的とする場合には、Oracleが提供している無償版 Oracle Database Express Edition(XE) を利用するのがおすすめです。
機能は限定されていますが、SQLの学習やデータベース作成の流れを理解するには十分。
インストールすれば自宅のPCで本格的なOracle環境を試せるため、初心者でも気軽に学習を始められます。
実務で触れる機会の多さ
Oracleは大企業の基幹システムに導入されていることが多いため、ITエンジニアとしてのキャリアを考えると学んでおいて損はありません。
特にインフラエンジニアやデータベースエンジニアを目指す方にとっては、Oracleの知識は 転職や昇給につながるスキル として評価されやすい領域です。
データベース作成の前提準備
Oracle Databaseを作成するには、まず実行環境を整える必要があります。ここでは最低限おさえておくべきポイントを解説します。
1. Oracle Databaseのインストール
まずはOracle Database本体をインストールしましょう。学習用であれば、無償で利用できる Oracle Database Express Edition(XE) を使うのがおすすめです。
Oracle公式サイトからダウンロード可能で、WindowsやLinuxに対応しています。
ダウンロードはこちらから
特別な設定がない場合は、基本的には「次へ」を押していけば大丈夫です。
2. 接続ツールの準備
Oracle Databaseに接続して操作するには、以下のツールを使います。
- SQL*Plus
Oracleに標準で付属するCLIツール。コマンド入力でデータベースの作成や操作が可能。 - SQL Developer(任意)
GUIベースの管理ツールですが、今回は紹介しません。学習を進めるうえではSQL*Plusだけで十分です。
3. 環境変数の設定
SQL*Plusを利用する際には、ORACLE_HOME や PATH などの環境変数が正しく設定されている必要があります。
インストール時に自動で設定される場合もありますが、コマンドが動かないときはここをチェックしましょう。
Oracleでデータベースを作成する方法
ここからは、実際にコマンドライン(SQL*Plus)を使ってデータベースを作成する方法を解説していきます。
1. SQL*Plusに接続する
まずは管理者権限でSQL*Plusに接続します。
sqlplus / as sysdbaSYSDBA 権限で接続することで、データベース作成や管理に必要な操作が可能になります。
2. CREATE DATABASE文の基本構文
Oracleでは、データベースの作成はCREATE DATABASE 文を使います。基本的な構文は以下のようになります。
CREATE DATABASE <データベース名>
USER SYS IDENTIFIED BY <パスワード>
USER SYSTEM IDENTIFIED BY <パスワード>
LOGFILE GROUP 1 ('/u01/app/oracle/oradata/db/log1a.rdo',
'/u01/app/oracle/oradata/db/log1b.rdo') SIZE 100M,
GROUP 2 ('/u01/app/oracle/oradata/db/log2a.rdo',
'/u01/app/oracle/oradata/db/log2b.rdo') SIZE 100M
MAXLOGFILES 5
MAXDATAFILES 100
CHARACTER SET AL32UTF8
NATIONAL CHARACTER SET AL16UTF16
EXTENT MANAGEMENT LOCAL
DATAFILE '/u01/app/oracle/oradata/db/system01.dbf' SIZE 500M
SYSAUX DATAFILE '/u01/app/oracle/oradata/db/sysaux01.dbf' SIZE 100M
DEFAULT TABLESPACE users
DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE temp TEMPFILE '/u01/app/oracle/oradata/db/temp01.dbf' SIZE 50M
UNDO TABLESPACE undotbs1 DATAFILE '/u01/app/oracle/oradata/db/undotbs01.dbf' SIZE 200M;ポイントは以下の通りです。
USER SYS/USER SYSTEM… 管理ユーザーの作成LOGFILE… リカバリに利用するREDOログの定義CHARACTER SET… データベースで利用する文字コード(日本語環境ならAL32UTF8が推奨)DATAFILE… データファイルの場所とサイズを指定TABLESPACE… データを格納する領域を定義
最小構成の作成例
学習目的であれば、よりシンプルな構文でも十分です。
CREATE DATABASE testdb
USER SYS IDENTIFIED BY password
USER SYSTEM IDENTIFIED BY password
CHARACTER SET AL32UTF8
DATAFILE '/u01/app/oracle/oradata/testdb/system01.dbf' SIZE 200M
DEFAULT TEMPORARY TABLESPACE temp TEMPFILE '/u01/app/oracle/oradata/testdb/temp01.dbf' SIZE 20M
UNDO TABLESPACE undotbs1 DATAFILE '/u01/app/oracle/oradata/testdb/undotbs01.dbf' SIZE 50M;このように最低限のパラメータを指定すれば、シンプルにデータベースを立ち上げることができます。
3. 作成後に行う初期設定
データベースを作成しただけでは不十分で、以下のような追加設定を行う必要があります。
ディクショナリの作成
基本的には、Oracleがインストールされた段階で自動的に作成されるものですが、万が一再作成が必要となった際には、下記のように入力してディクショナリを作成します。
@?/rdbms/admin/catalog.sql
@?/rdbms/admin/catproc.sql
ユーザー作成や権限付与
CREATE USER appuser IDENTIFIED BY apppass;
GRANT CONNECT, RESOURCE TO appuser;こうした設定を行うことで、実際にアプリケーションから利用できるデータベース環境が整います。
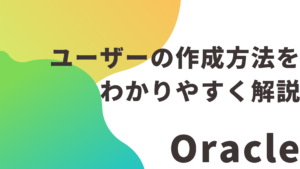
作成後の確認と基本操作
データベースを作成したら、そのままにせず 正しく動作しているか確認 しておくことが大切です。ここでは、Oracleでよく使う基本操作を紹介します。
1. インスタンスとデータベースの関係
Oracleでは「インスタンス(メモリ+プロセス)」と「データベース(データファイル群)」が別物として存在します。
- インスタンス:メモリ領域(SGA)とプロセス群
- データベース:ディスク上のデータファイル
そのため、作成後には インスタンスが正しく起動してデータベースと接続できるか を確認する必要があります。

2. インスタンスの起動・停止
SQL*Plusから以下のコマンドを実行します。
-- インスタンス起動
STARTUP;
-- インスタンス停止
SHUTDOWN IMMEDIATE;STARTUP を実行すると、インスタンスの起動→データベースのマウント→データベースのオープン、という順序で処理が行われます。
3. データベースの状態確認
現在のデータベースの状態を確認するためには以下を実行します。
SELECT INSTANCE_NAME, STATUS FROM V$INSTANCE;結果がOPEN になっていれば、データベースは利用可能な状態です。
4. 接続状態確認(ユーザーでログイン)
作成したユーザーでログインしてみましょう。
sqlplus appuser/apppass@testdbログインできれば、アプリケーションからも利用できる状態になっています。
5. ユーザー作成と権限付与
データベース利用の基本は「ユーザーを作って権限を与える」ことです。
CREATE USER sample IDENTIFIED BY samplepass;
GRANT CONNECT, RESOURCE TO sample;これで sample ユーザーが自由にスキーマを作成できるようになります。
このように、作成後は 起動・停止 → 状態確認 → ユーザーで接続 という流れをひと通り試しておくと安心です。
まとめ
本記事では、Oracle Databaseの作成方法について、コマンドラインを用いた実務寄りの手順 を中心に解説しました。
- Oracleの基本を理解する
- インストールと環境準備
CREATE DATABASE文によるデータベース作成- 作成後の起動・確認・ユーザー作成
ここまでの流れを実践すれば、単なる「使い方を知っている」から一歩進んで、自分でOracle環境を立ち上げられるレベル に到達できます。
さらに深く学ぶための書籍
Oracleは機能が非常に豊富で、現場で使いこなすには体系的な知識が欠かせません。学習を進める際におすすめの書籍をいくつかご紹介します。
図解入門よくわかる 最新Oracleデータベースの基本と仕組み
図解で解説されている箇所が多く、初心者が全体像を理解するのに最適です。
Oracleの現場を効率化する100の技
初心者からベテランまで、経験レベルを問わず活用できる一冊で、Oracle Databaseユーザー必携の実践書 といえます。
忙しい現場でも、効率的に学びながら実践できる点が魅力。
キャリアアップにつなげる
Oracleの知識は、データベースエンジニア・インフラエンジニア を目指すうえで大きな武器になります。特に大企業や金融・通信業界などでは、Oracleスキルを持っている人材が高く評価される傾向があります。
転職を視野に入れるなら、ITエンジニア特化の転職サイトを活用するのがおすすめです。おすすめの転職サイトを以下の記事にまとめておりますので、ぜひご覧ください。
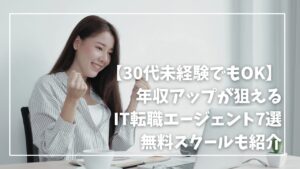
「自分でOracleデータベースを作れる」という経験は、エンジニアとしての自信にもつながります。
ぜひ今回の内容を実践し、書籍や転職サイトも活用しながら、学習とキャリアアップの両立 を目指してみてください。
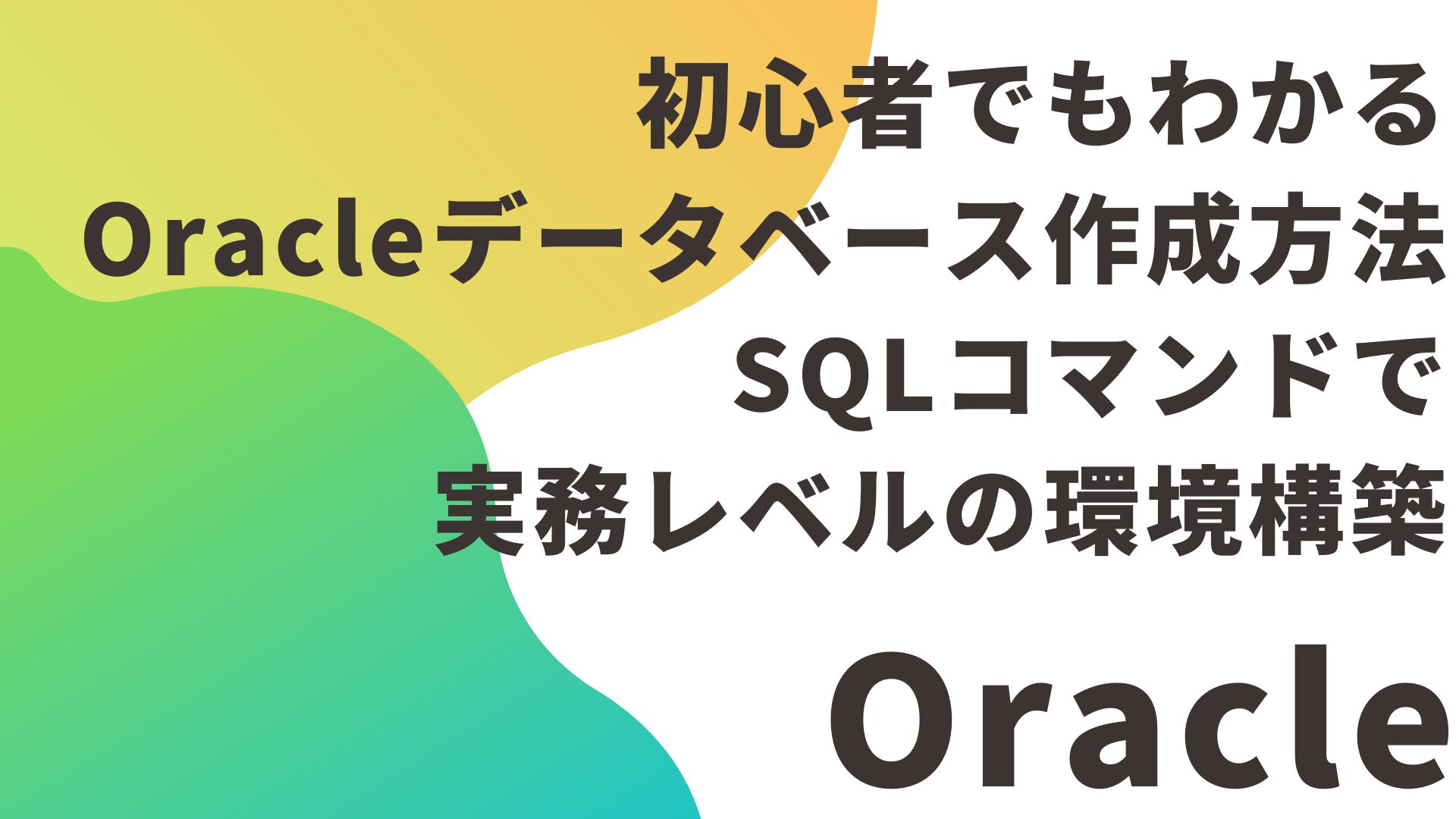

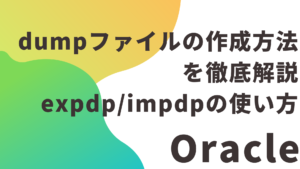

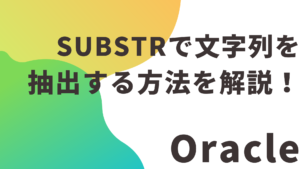
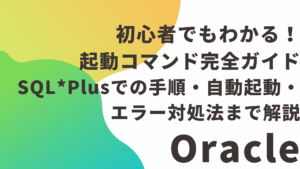
コメント